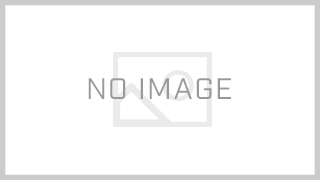葛籠の中身
リナは、太陽が昇る前の鳥の鳴き声と共に目覚め、静かな田舎町での朝を迎えた。彼女の金色に輝く髪は、まだ眠い青い瞳を枠取り、頬は若さが伝える純真なピンク色に染まっていた。しかし、その目は次第に現れる現実に耐えかねていた。
彼女の一日は、毎日のように、学校への通学とタケオとの甘い時間、そしてランとの友情に満ちていた。しかし、学校裏の森へと続く道に初めて足を踏み入れたとき、リナの平穏な日常は微妙に揺らぎ始めた。
彼女が初めて森を訪れたのは、一本の葛籠を探すためだった。その道中で、リナはどこか異様な臭いに気づいた。それは、腐った果実のような、甘くて腐敗した香りだった。彼女の心は、未知の恐怖を予感させる脈動を感じ始めていた。
森の中で見つけた葛籠は、内部が何かで満たされていた。それは見るからに不健康な色の何かで、リナの目には異様に見えた。彼女の手が葛籠を掴むと、その柔らかさと温かさに身震いした。
その夜、リナは異様な夢を見た。自分が葛籠の中の異様な物体を食べている夢だった。口の中に広がるその味は、生肉と腐った果実の間のような不快なもの
だった。しかし、夢の中のリナは、その味に引き寄せられ、自制心を失って食べ続けていた。
日々が過ぎるにつれ、リナは再び葛籠を訪れ、その中身に取り憑かれるようになった。葛籠の中身が無くなると、彼女は森を彷徨い、新たな葛籠を探した。森の深部から聞こえる不気味な音、風に乗る腐ったような甘い香り、それらは彼女をより深く森へと誘い込んだ。
リナは次第に痩せ、金色の髪は枯れ、青い瞳は虚ろになっていった。タケオとランは彼女の様子に心配を抱きつつも、彼女が何に取り憑かれているのか理解できなかった。リナ自身も、自分が何を求め、何を食べ続けているのか理解できず、ただただその衝動に従っていた。
ついにリナは自分が何を食べているのか理解した。それは森の生物、恐らくは人間だった。それは葛籠に詰められ、彼女に供されていた。彼女の心は恐怖で満たされ、しかし彼女の身体は止まらなかった。
彼女は逃げ出そうとしたが、森は彼女を放さなかった。森の中にはもはや出口は存在せず、彼女は彷徨い続けるしかなかった。彼女の恐怖と絶望は彼女自身を食べ尽くし、彼女の精神は破壊されていった。
最後にリナが見たものは、自分の手が葛籠を掴んでいる光景だった。彼女の顔は恐怖で引きつり、しかし彼女の口は未だに葛籠の中身を食べていた。彼女の心はもはや絶望しかなく、彼女の身体は森の一部となっていた。彼女は最後まで葛籠の中身を食べ続け、そのまま消えていった。その最後の瞬間、彼女の脳裏に浮かんだのは、タケオの温かな笑顔とランの優しい声だけだった。
森は静寂に包まれ、リナの存在は完全に消え去った。ただ、その恐怖は森の中にずっと残り、語り継がれることとなる。そして、葛籠はまた新たな犠牲者を待ち続けるのだった。