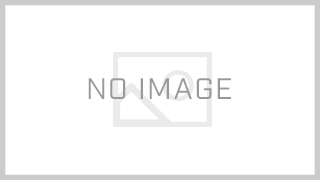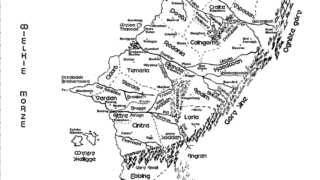岡田以蔵 – 幕末の人斬りから英霊へ
岡田以蔵 – 幕末の人斬りから英霊へ
はじめに
幕末という動乱の時代に生きた刺客、岡田以蔵(おかだいぞう)。彼の名前は、歴史書の一節に「土佐の人斬り」として記されています。今回は、この謎めいた暗殺者の実像と、スマホゲーム「Fate/Grand Order(FGO)」において英霊として召喚される岡田以蔵について詳しく解説します。史実としての岡田以蔵とFGOのキャラクターとしての岡田以蔵、その両面から迫っていきましょう。
史実の岡田以蔵
生い立ちと若年期
岡田以蔵は、天保8年(1837年)、現在の高知県高岡郡中土佐町久礼(当時の土佐国高岡郡久礼浦)で生まれました。父は「岡田弥太夫」、母は「おかつ」という名でした。出生時の名前は「岡田井蔵」であり、後に「以蔵」と表記されるようになりました。
土佐藩の社会的身分制度において、以蔵は「郷士(ごうし)」というやや曖昧な位置にありました。郷士とは、完全な武士ではないものの、一般の農民より上位の階級に位置する存在です。彼は裕福ではありませんでしたが、極貧というわけでもなく、一定の教育を受けることができる環境にありました。
幼少期の以蔵については詳細な記録は多くありませんが、気性が激しく、向こう見ずな性格だったと伝えられています。地元では腕っぷしの強さで知られるようになり、若くして喧嘩や争いごとに関わることも少なくなかったようです。
剣術の修行と技術
以蔵が歴史に名を残す「人斬り」となる基礎を築いたのは、彼の優れた剣術の腕前でした。15歳の頃から土佐藩の剣術指南、千葉周作の道場に入門し、北辰一刀流を学びました。千葉道場では、後の新選組局長となる近藤勇や、同じく新選組の沖田総司らも修行しており、幕末の剣豪たちと同じ時期に修練を積んでいたことになります。
以蔵の剣術の特徴は、型にはまらない自由な動きと、相手の動きに合わせて瞬時に反応する速さにありました。彼は正統派の剣術を基礎としながらも、実戦で使える独自の技術を発展させていきました。特に、抜刀術(居合)に関しては非常に優れており、一瞬の隙を見逃さず刀を抜いて斬りつける技はまさに暗殺者に相応しいものでした。
土佐に戻った後は、「神道無念流」「示現流」など、土佐藩に伝わる剣術も学んだとされています。また、彼が拠点としていた高知城下の廓(くるわ)周辺での喧嘩や果し合いを通じて、実戦経験を積んでいきました。
剣の腕前に関しては、当時の一流の剣士たちからも一目置かれる存在となり、「人斬り以蔵」という異名を得るずっと以前から、その実力は広く認知されていました。
土佐勤王党との関わり
幕末の土佐藩では、武市瑞山(たけちずいざん)を中心とした「土佐勤王党」が組織され、尊王攘夷運動を展開していました。武市瑞山は郷士階級の知識人であり、同じく郷士階級出身の以蔵を党に引き入れました。
安政5年(1858年)、以蔵は21歳の時に土佐勤王党に加わります。勤王党の中では、頭脳派というよりは実行部隊として期待されていました。文学や思想に深い理解を持っていたわけではなく、「尊王攘夷」の思想的な内容よりも、具体的な行動で貢献することを求められていたのです。
土佐勤王党の活動において、以蔵は「人斬り」として頭角を現していきます。武市瑞山の指示のもと、幕府の支持者や攘夷に反対する人物の暗殺を担当するようになりました。以蔵にとって、これらの暗殺任務は自らの剣の腕を試す場であると同時に、土佐勤王党内での自分の居場所を確立する手段でもありました。
暗殺者・人斬りとしての活動
以蔵が「人斬り以蔵」として歴史に名を残す活動を本格的に始めたのは、文久2年(1862年)頃からです。京都を中心に活動し、勤王党の指示に従って幕府支持者や反対派の暗殺を行いました。
以蔵の暗殺術は非常に効率的でした。彼は標的を徹底的に調査し、習慣や行動パターンを把握した上で最適なタイミングを選んで攻撃しました。多くの場合、夜間や人気の少ない場所で背後から一撃を加えるという方法を用いていました。その正確さと冷酷さから、「土佐の人斬り」として恐れられるようになりました。
以蔵が暗殺したとされる人物の正確な数は不明ですが、少なくとも数十人に上るとされています。特に有名なのは、文久3年(1863年)に起きた「八月十八日の政変」の際に、公家の三条実美らを追放するよう働きかけた島田左近の暗殺です。この暗殺は、以蔵の名を一層高めることになりました。
しかし、こうした暗殺活動は以蔵自身の精神にも大きな影響を与えていました。当初は義に基づいた行動だと信じていたものの、次第に「誰のために、何のために人を斬っているのか」という疑問を抱くようになっていったと言われています。特に、土佐勤王党が幕府側と和解し方針を転換すると、以蔵は精神的に不安定な状態に陥ったとされています。
逮捕と最期
慶応3年(1867年)、時代の流れは大きく変わっていました。徳川幕府は大政奉還を行い、武力での抵抗を諦めつつありました。かつての尊王攘夷派の多くは佐幕派と和解し、新たな時代への移行を模索していました。
しかし、以蔵はこうした時代の変化についていけませんでした。彼は依然として「人斬り」としての活動を続け、新政府側にとっても危険人物と見なされるようになりました。
慶応4年(1868年)1月3日、江戸の品川で石清水八幡宮の神官・長松清風を暗殺しようとしたところを捕らえられました。新政府は以蔵を投獄し、裁判にかけました。裁判では、以蔵は多くの暗殺を認め、自らの罪を受け入れたと言われています。
同年5月11日(明治元年4月19日)、以蔵は獄中で首吊り自殺をしたとされています。しかし、この死因については諸説あり、処刑されたという説や、自殺に見せかけて殺害されたという説も存在します。享年31歳でした。
以蔵の最期は、彼が生きた時代そのものを象徴するようなものでした。新しい時代の幕開けとともに、幕末の暗殺者としての役割を終えた彼は、明治という新たな時代に足を踏み入れることなく、歴史の舞台から姿を消したのです。
歴史的評価と伝承
岡田以蔵の歴史的評価は非常に複雑です。一方では冷酷な暗殺者として恐れられ、他方では時代に翻弄された悲劇的な人物として同情される存在でもあります。
歴史家の中には、以蔵を単なる殺し屋として否定的に評価する人もいれば、尊王攘夷の志士として肯定的に見る人もいます。しかし、多くの歴史家は、以蔵を「時代の犠牲者」として位置づけています。彼の剣術の腕前が買われ、政治的な駒として利用された側面は否定できません。
以蔵の死後、彼の伝説は様々な形で語り継がれました。小説、映画、ドラマなど多くの創作作品の題材となり、「最後の人斬り」として描かれることが多くなりました。特に、司馬遼太郎の小説「燃えよ剣」や、子母澤寛の「勝海舟」などでは、以蔵の人物像が鮮やかに描かれています。
また、高知県中土佐町久礼には、岡田以蔵の生家跡や墓があり、地元では郷土の偉人として記憶されています。毎年5月11日には命日に合わせて慰霊祭が行われ、彼の複雑な生涯を偲ぶ人々が訪れます。
以蔵の存在は、幕末という動乱の時代を生き抜いた一人の剣士の姿を通して、日本の近代化の過程で置き去りにされた人々の象徴としても理解されています。
史実とFGOの比較
FGOにおける岡田以蔵の描写は、基本的に史実に忠実な部分が多いですが、ゲームの世界観に合わせた脚色も加えられています。
共通点:
- 土佐の郷士出身であること
- 卓越した剣術の腕前を持っていること
- 「人斬り以蔵」として暗殺活動に従事していたこと
- 武市瑞山、桂小五郎、坂本龍馬という三人の「主人」に仕えた経験があること
- 時代の変化についていけず、最終的に孤立した人物であること
相違点:
- FGOでは「心眼」や「無十文字」といった超人的な能力として表現されている部分
- 史実では暗殺者としての冷徹さが強調されることが多いが、FGOでは粗野ながらも人間味のある性格として描かれている
- FGOでは「人斬り」であることに誇りを持つ姿が強調されているが、史実の以蔵がどう思っていたかは定かではない
FGOの岡田以蔵は、史実の彼が持っていた「時代に翻弄された悲劇的な人物」という側面を深く掘り下げつつ、ファンタジー要素を加えて魅力的なキャラクターとして再構築されていると言えるでしょう。
まとめ
史実の岡田以蔵は、幕末という激動の時代に「土佐の人斬り」として名を馳せた暗殺者でした。優れた剣術の腕を買われ、政治的な駒として利用された彼の生涯は、まさに時代の縮図とも言えるものでした。
一方、FGOにおける岡田以蔵は、その歴史的背景を丁寧に取り入れながらも、独自の解釈を加えたキャラクターとして描かれています。「人斬り」であることに誇りを持ちつつも、自分の生き方に対して常に問いかけを続ける姿は、多くのプレイヤーの心を掴んでいます。
彼の存在は、私たちに「歴史とは何か」「英雄とは誰か」という問いを投げかけているようにも感じられます。暗殺者として恐れられた人物が、現代において英霊として召喚され、人類の危機に立ち向かう存在として描かれる。そのギャップこそが、FGOというゲームの魅力の一つであると言えるでしょう。
史実とフィクションが交錯する岡田以蔵の物語は、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。