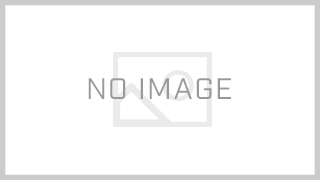ある町に名探偵・沙耶がいた。名探偵と称されながら、彼女はいわゆる顔が見えるタイプではない。口を利くことは少なく、行動が主であった。それでも町の人々は彼女を信頼していた。それはなぜかというと、彼女の結果がものを言っていたからだ。
ある日、彼女のもとに奇妙な依頼が舞い込んだ。「幽霊に会いたい」という。町の郊外に住むお年寄りからのものだった。依頼は非日常的だったが、奇妙な依頼が日常の一部である沙耶にとっては、なんてことはない。
「ああ、そういうのは得意じゃないけど、試しにやってみようかな。」
彼女は口数が少ないわりに笑顔が絶えない。それは奇妙な魅力を持つ彼女の一面だ。そして、その笑顔の背後には、人知を超えた知識と洞察力があった。
幽霊が現れると言われる古い洋館へと向かった。朽ち果てた木々が道を覆い、空気はいつもより濃い霧で覆われていた。太陽が落ち、月が出ると、その霧は光を放つ。それが洋館への道を照らしてくれた。
「まあ、何というか、この場所は確かに幽霊が出そうだね。」
と、沙耶は霧のなかでつぶやいた。洋館への石畳の道を進みながら、彼女は前方に目を向け、そこに何かを探していた。
洋館に到着し、彼女はその大きな扉を開けた。軋む音が洋館全体に響き渡った。中は暗く、彼女の視線を飲み込んでいった。
「ホラー映画に出てきそうな場所だね。」
彼女が言いながら、扉を開けた瞬間、何かが足元を掠めていったような気がした。彼女はそれを無視せず、足元を見つめる。しかし、何も見えなかった。
夜が更けてきたころ、部屋の隅から何かが沙耶を覗いているような気配を感じた。足元の冷たさが、その存在を教えていた。
「あなたが、私を見ているの?」
彼女はゆっくりとそちらに向き直り、周囲を見回した。しかし、見えるものは何もなかった。彼女の頬には、冷気が触れていた。震える指先で、彼女は自身の頬を撫でた。
「あなたがいるなら、何か声をかけてみてよ。」
そして、その瞬間。洋館全体が揺れ、天井から落ちるほこりが部屋全体を覆った。沙耶は硬直したまま立っていた。
その後、何度も洋館を訪れたが、幽霊との接触はもうなかった。しかし、その存在感、その冷気は、彼女の中に深く刻まれた。
この物語の終わりがどうなるかは、私たちには分からない。それは沙耶だけが知る、沙耶とその幽霊だけが知る、物語の終わりだ。しかし、その終わりが何であれ、私たちが知ることはできない。なぜなら、それは語られない恐怖だからだ。